こんにちは、ハルです。
今回はゲームに関する記事です。
今回は大人気(諸説あり)MMO(諸説あり)RPGゲームであったブループロトコルに関する記事です。
前回の記事の続きです。(↓)
さて前回の記事では、個人的にすごく高評価のブループロトコルが「なぜ短期サ終に追い込まれたのか」という理由について、特にお金の観点から考えてみました。
今回は続きです。「何が悪くて短期サービス終了してしまったのか」などについて私なりの考えを述べたいと思います。
・当記事ではゲーム内画像などを多く紹介しておりますが、知的財産権等の権利はすべて運営者様に帰属しており、権利の侵害は意図しておりません。何か問題ありましたらお問い合わせフォーム等よりご連絡いただければ速やかに対応いたします。
BLUE PROTOCOL
©2019 Bandai Namco Online Inc. ©2019 Bandai Namco Studios Inc.
前置き:要するにお金を稼げなかったからだが……
前置きです。
前回の記事ではブループロトコルの失敗について、お金という観点から考えていきました。
ざっくり前回の記事を要約すると
・開発費100億円。もしかすると131億円
・毎月のランニングコストに最低1億円。下手すりゃ数億
という試算をしてみました。
(企業経営の経験など全くないド素人の浅はかな試算なので、ランニングコストに関しては実際は数倍かかっている可能性があります。)
特に構想含めて8年もの開発期間によって生じた100億円もの開発費の負担が重すぎます。
その上で、うまくゲーム運営を行えなかった。お金を儲けられなかった。その失敗の原因について考えていきます。
短期サ終・失敗の具体的理由(ゲーム内)
初手で大失敗:プレイヤーを繋ぎ止められなかった
前回の記事でもご紹介しましたが、ブループロトコルは国産MMORPGとしてかなりの注目を集めました。間違いなく需要はありました。
2023年6月14日のサービス開始からわずか1週間で「累計プレイヤー数60万人&最大同時接続プレイヤー数20万人以上突破」という偉業を達成。約半年後には累計100万を達成。
しかしですね。100万人という数字は基本無料だからこその数字です。
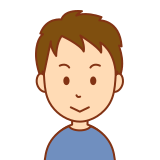
なんか無料の新作MMOが出たみたいだからとりあえず触ってみるか
無料だからとりあえず遊んでみるかが大多数。最初は当然お金を払うつもりなどありません。
無課金プレイヤーが100万人居たところで、1円も儲かりません。それどころかサーバーに負担がかかるマイナスの効果さえ生じます。
とはいえプレイヤー数の絶対数は賑やかしとして重要。将来のお客様候補として、まずは広く門戸を開く姿勢を取ることは言うまでもなく大事です。
その来てもらったプレイヤー諸氏をどうやって繋ぎ止めるか。ゲームを続けて貰うか貰うか。
もっと言うと「どうやってお金を出して貰うか」というマネタイズが運営の手腕の見せ所なのですが、ブルプロ運営は初手で失敗をしました。
初動でズッコケた結果、「これは触るに値しないゲームだ」と判断の早いプレイヤーに愛想を尽かされてしまい、バグだらけなどのとんでもない悪評が広がり、そのままズルズルと過疎、そしてサ終への道を歩んでしまったのだと思います。
では具体的にどういう点で初手を誤ったのかというと
・初日ログインできず夜中まで緊急メンテ (まあこれは新作ゲームのお約束みたいな感はありますが)
・バグだらけでゲームにならん :無限ロード、クラッシュ、エラーコード、フリーズ、同期エラー
・極悪な青天井ガチャ :改善前は最高レアが1.2%だった。のちに3%に
・必要ない労力を必要ない場所にかけた
・大昔の古いMMOと最近のソシャゲの悪いところのミックス
・あまりに廃仕様・鬼畜なβスキルのドロップ率 :ダンジョン100周しても出ないとか?
・アイテムトレードがない、店売りが出来ない
・メニューのUIが稚拙
・お排泄なミッションボード
・課金したくなるものが何も無い
などがあります。
いくつか取り上げて項目としてご説明します。
なお最初の緊急メンテやバグ等は、まあ新規ゲームのサービス開始時なので多少は大目に見るべきものだとも思います。
必要ないグラフィックにこだわりすぎた
ブループロトコルをプレイしたことが無い方も、こんな記事をご覧になったことはあるかも知れません。
『ブループロトコル』の「キャベツ」がやたら作り込まれていると話題。葉脈まで描かれた高精細キャベツ
https://automaton-media.com/articles/newsjp/20230619-252490
『BLUE PROTOCOL(ブループロトコル)』のキャベツが、やたら作り込まれているとして話題になっている。本作の中ではキャベツのモデリングが野菜の中で別格であると指摘され、話題として広まっているようだ。
実は私もブループロトコルのプレイ前にこの記事を見たことがありました。
そして実際にブルプロ世界にダイブして目撃したキャベツがこちら!!!

いや、確かにめっちゃリアルだわ(笑)

無駄にリアルな高精細キャベツがゴロゴロしています。
しかしこれは「スタッフのこだわりがアツい」とか「話題になって良かったね」という次元の話ではなく「必要ない労力を必要ない場所にかけた典型例」ではないかなと思うのです。
ゲーム開発に捧げられるリソースは有限なので、主要コンテンツにリソースを注力して力を入れて、大して重要でもない箇所はうまく手を抜くことも大事ではないかと思うのです。
キャベツが美しいのはまあ良いとしても、改善するべきUIやゲーム性の改善やバグ取りなどは手つかずで残されたままです。美しいキャベツの代償としてはあまりに重い。

こんな例もあります。これはとある町の家の中のスクショなのですが、何の変哲もないただの民家ですがびっくりするくらい美麗グラフィックだと思います。光の表現なんかもレベル高いです。私も感心してスクショを撮りました。
しかし実機でこの家の中を見たプレイヤーが果たして何人いたことか。これどこの町にある家か分かりますでしょうか。ジュビリアの水上ハウスの中なのですが。
実は同じような話が、FF14でもありました。
今でこそ大人気でブループロトコルなど足元にも及ばない雲の上の存在であるFF14ですが、実は初期に開発されたものは大失敗して一から作り直したという経緯があります。いわゆるFF14根性版と呼ばれるものです。
このFF14、ブループロトコルと全く同じ失敗をしていました。
「旧FFXIV」は、「WOW」をターゲットとして設定しながら、プレイ体験で差別化を図る方針だったにも関わらず、とにかくグラフィックスにこだわってしまったことが間違いであることを強調した。
吉田氏は一例として、街に置かれるフラワーポット1つに、1,000ポリゴン、150ラインのシェーダーコードが使われていたことを明かし、「これはキャラクターと同じ処理負荷、PCの表示数を20人に制限するという判断が行なわれていた」と信じられないという雰囲気で語った。
まとめとして吉田氏は、「旧FFXIV」の失敗の理由として3つを挙げた。ひとつはグラフィックスクオリティに固執しすぎたことで、大事なのはゲーム体験であるべきだとした。
【GDC 2014】「新生FFXIV」吉田Pが、「旧FFXIV」が失敗した理由を余さず語る
いかがでしょう。ちなみにFF14(根性版)のリリースは2010年です。そして大失敗して2012年にサ終しました。どこかで見た流れだな……
ブループロトコルはこのFF14の失敗から全く学ばず、自社のゲームに生かせていないように思えます。同じMMORPGで競合他社での事例であるにもかかわらず同じ失敗をするようでは、業界研究が足りなかったと言わざる得ない結果だと思います。
大昔の古いMMOと最近のソシャゲの悪いところのミックス
これは私も体感したことですが、ブループロトコルは
・おつかい&おつかい&採取&討伐&おつかい&トコヨ草
・ダンジョン潜り&潜り&潜り&潜り
という太古のMMOでよく見られた要素が多く存在します。
MMOである以上おつかいは仕方ないとも思うのですが、そこを単調にならず楽しませるのも運営の手腕の見せ所。肝心の出来はというと、残念ながら楽しいとは思えない感じでした。
また、私は体験していないのですが、ブループロトコルには装備品の代わりになるβスキルというものがありました。これを入手するためにはダンジョンに潜って敵のドロップからの入手を狙うのですが、このβスキルを作る材料のドロップ率があまりにも低すぎた。経験者曰く、100周しても出ないとかザラだったそうです。
これも太古のMMOの負の側面です。ダンジョンに何度も潜ってレアドロップ品を探し求めるというのも確かに楽しみの1つではあると思うのですが、娯楽の乏しかった昔ならいざ知らず、娯楽があふれていていくらでも時間を消費できる現代で、ダンジョン100周はちょっと時代錯誤というか、まともなプレイヤーは付いてこれないと思います。
そうかと思えば最近のソシャゲでよくある要素、つまりガチャでの集金がメインという、これではお客さんは納得しないよなあと思わざるを得ません。
P2Wをしないという決断には敬意を表するが……
ゲーム用語にP2Wというものがあります。
P2WとはPay to Winのことで、「お金を払えば勝てる」と言った意味合いです。
類語にF2P、F2Wなどがあります。それぞれFree to Play(無料でプレイできる)、Free to Win(無料でもプレイヤー次第で勝てる)の略です。
P2Wの一番分かりやすい例は、例えばレスナスストア(課金ショップ)に最強の剣エクスカリバーが5万円で売ってる、とかでしょうか。
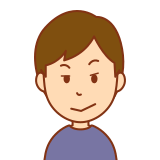
5万円を払えば誰でも最強の武器が手に入る!!これでヴォルディゲンもワンパン!!!
で、ブループロトコルは運営の方針としてP2Wはしないとされています。プロデューサーもそう言っています。
P2Wには賛否両論あって「金を払えばなんでもアリか、この拝金主義者め」という否定的な意見や、「初心者がすぐ前線に追いつける」「強い装備は課金の正当な対価」という肯定意見があって議論になりがちなところですが、ブループロトコルではP2Wは行わないと。
個人的にはあまり金儲けを前面に押し出されると萎えるのでこのブルプロ運営の判断には敬意を表しますが、では代わりにどこでお金を得るのか、という大事な問題があります。
P2Wしないならユーザーにどこでお金を使ってもらうのか。
ブループロトコルの場合、課金は「衣装・エモーション・マウント(移動に使える乗り物)」などがメインでした。
つまり無料でプレイできるし無料でもそこそこ勝てるけれども、衣装に拘りたい人は課金してね、というスタンス。
これはブループロトコルに最後まで残った層、つまりキャラ愛勢をターゲットにした課金手法で私としては正確な判断だしこの姿勢は好ましいとも思うのですが、結果としては全然儲かりませんでした。
つまり衣装ではお金を稼げなかったということ。
これはキャラ愛勢がケチとかそういう話ではなく、「欲しくなる衣装が無かった」「欲しくなるコンテンツが無かった」という運営の失敗だと思います。実際、苦労して衣装を手に入れてみたら上下セットで使いにくいとか、表示が崩れてしまっているなどの声を耳にしました。
課金したくなるものがない
ブループロトコルを遊んだプレイヤーの中には
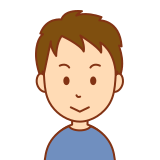
なんだ、そこそこ面白いじゃないか。課金することもやぶさかではないが……
と思ってくれた人も少なからず居た事でしょう。
しかし残念ながら、ゲーム内に課金する対象が無かった。課金したくなるものが無かった。
例えば衣装にしても上にも書きましたが、強制的に上下がセットになっていたり、モデリングが雑で表示が崩れてしまっている物もあったようです。
たしかに私もブループロトコルの最期の二週間をプレイした中で、あまり印象に残った衣装というのはありませんでした。変な着ぐるみとかスク水とかは記憶に残ったけれども。

(↑) 変な着ぐるみ。いっそこういう突き抜けた面白い衣装系で攻めるのも手だったのかも。なお右のおじさんはただのNPC
その一方で、課金するとキャラの見た目を変更できるパスを入手できるみたいなのもありました。
個人的にはこの集金方法のアイディアはなかなか良いんじゃないかと思うのですが、実際には不評だったそうです。私は実際には経験していないのでどのような点で不評だったのかはいまいち分かっていません。価格設定の面の不満なのかどうなのか。
「見た目くらい自由に変えさせろ」という強欲な声なのか、はたまた価格が高すぎたのか。
でもゲーム攻略には直接影響しない「キャラの外見」で課金を促すという考え方自体は間違っていなかったのではないかとも思います。
プレイヤーが望んでいたものと実際に提供されたものとの乖離
ブループロトコルを遊ぼうと思ってインストールしたプレイヤー諸君は、ブルプロに何を期待して何を望んでいたでしょうか。
こればっかりは想像するしかないですが
・アニメ調の世界でほのぼの生活
・ギルドで交流、ギルド専用のスペース
・ハウジングなどの装飾、生産要素など
・MMOらしく他プレイヤーと協力してのチーム戦やレイドバトル、あるいは対人戦
などでしょうか?
では実際に提供されたものはどうだったかというと
・ダンジョン周回
・タイムアタック
・上級調査
・上級調査改
・ラッシュバトル
・連綿の塔・トコヨ草
うーん。もちろんこれだけではないのですが、あまりにもアクション要素が強すぎるラインナップだと思いました。とにかく、戦闘以外のコンテンツがほぼ皆無と言って良い状況。
実際、ブループロトコルは途中からアクションゲームに舵を切ったようです。MMOアクションRPGとしてそれなりの出来栄えにはなっていて、これはこれで楽しめたのは事実なのですが、せっかくブループロトコルをインストールしてくれたプレイヤーが求めていたものとは乖離していた可能性があります。
ちなみに私はこの提供された戦闘コンテンツの全てに見向きもせず、ブループロトコルの世界のお散歩とスクショとプレイヤーの観測だけで十二分に楽しめました。
ゲーミングPC必須やはりハンデか
ブループロトコルをプレイするためには基本的にゲーミングPCが必要になります。
性能自体は(どこかを妥協すれば)エントリークラスのものでも十分遊べるのですが、やはりゲーミングPC必須はかなりハンデなのかなと……。
私などはスマホなどはどこまで行ってもおもちゃでしかない、クリエイティブ作業やゲームやブラウジングなど何をするにしてもPCがない生活などありえないという認識ですが、どうやら世間一般ではもうPCを持っていない人もそれなりにいるそうです。信じられん。
しかも普通のPCではダメで、ゲーミングPCです。昨今の物価高やAI需要やマイニング需要などでゲーミングPCはめちゃくちゃ値上がりして、もうキッズにはそう簡単には手が出ない価格帯になっています。そのためゲーミングPCを持っているのはある程度の所得のある年齢層か、はたまたオタクかという感じ。
そしてオタクはともかく、ある程度の大人は1つのゲームに何十時間もかけてダンジョンを100周する時間など取れません。
そういう意味でMMOというゲームコンテンツ自体の限界を感じますし、運営にはやはり逆風でしょう。
間口を広げるための切り札になりえたPS5版とxbox版は、劣悪UIとバグでまともに遊べずサービス開始からすぐに撃沈してしまいました。
コンシューマ機でしっかり遊べるようなゲームを作れれば、まだまだ人口が増える可能性があったと思います。これも運営の失敗です。
ということで今回はここまでにします。
今回はブループロトコルはなぜ短期サ終に追い込まれたのかに関して、ゲーム運営の面から考えてみました。
次回は「ではどうすれば良かったか」を考えます。
それではまた。ご覧いただきありがとうございました!
続きです(↑)


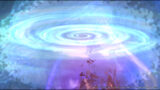
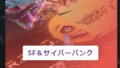

コメント